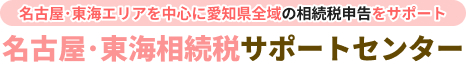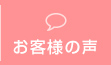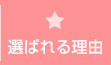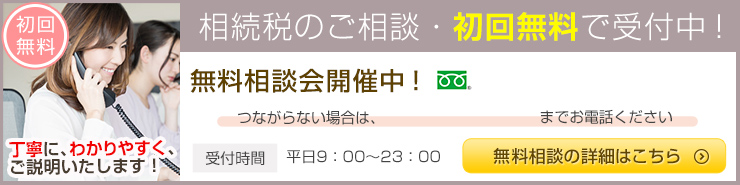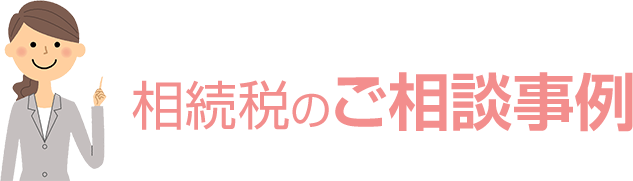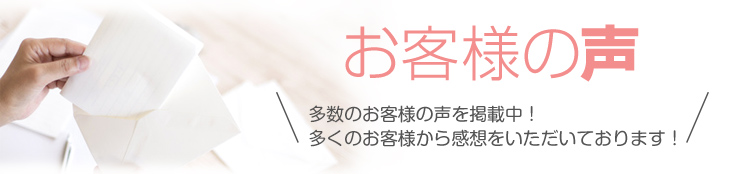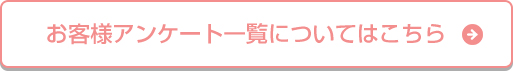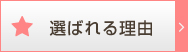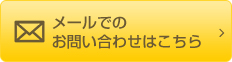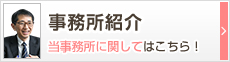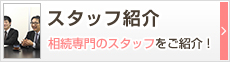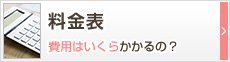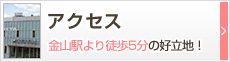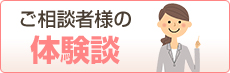相続税と贈与税の違いを解説!どちらがメリットが大きいのか徹底比較

「相続税と贈与税って、どう違うの?」
身内の不幸や将来の資産承継を考える中で、こんな疑問を持ったことはありませんか?
どちらも「財産を受け取ったときに関係する税金」ではありますが、課税のタイミング・税率・申告方法などに明確な違いがあります。これらの違いを正しく理解しておかないと、本来より多くの税金を支払ってしまったり、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
特に近年では、相続税の課税対象となる方が増加傾向にあり、生前贈与による対策を検討する方も増えています。しかし、贈与にも贈与税がかかるため、単に「生前に渡せば安心」というわけではありません。
この記事では、相続税と贈与税の違いをわかりやすく解説し、それぞれの制度の特徴や適用の注意点を紹介します。これから資産の引き継ぎを検討している方や、ご家族の相続を控えている方にとって、後悔しない判断をするためのヒントとなれば幸いです。
相続税と贈与税の定義とは?
相続税と贈与税は、どちらも財産を受け取った人に対して課される税金ですが、課税の場面や対象が異なるため、しっかりと区別することが大切です。
相続税とは
相続税は、人が亡くなったときに、その人の財産を相続や遺贈によって取得した人に課される税金です。例えば、亡くなった親の預金や不動産を子どもが引き継いだ場合、その取得した財産の価額に応じて相続税が発生します。
また、相続税は「被相続人(亡くなった人)」の死亡を契機として発生するため、取得の意思に関係なく、法定相続人であるかどうかも含めて課税対象になります。
贈与税とは
一方で、贈与税は、生きている人から財産をもらった場合に課される税金です。たとえば、親が子どもに毎年お金を渡しているような場合、その金額によっては贈与税の課税対象となる可能性があります。
贈与税は、基本的には1年間(1月1日〜12月31日)の間に受け取った贈与の合計額に対して課税され、受け取った人が申告・納税する義務があります。
共通点と相違点
どちらも「財産を無償で受け取った場合」に課税されるという共通点がありますが、発生するタイミング・税率・申告義務者などに違いがあるため、混同しないことが重要です。
相続税は亡くなった後に発生し、贈与税は生前の財産移転で発生する――この基本的な違いを押さえておくことで、節税や適切な財産管理の第一歩となります。
相続税と贈与税の税率の比較
相続税と贈与税では、税率の構造に共通点はあるものの、実際の負担額には大きな違いが生まれることがあります。
ここでは、それぞれの税率体系とその違いをわかりやすく比較します。
相続税の税率構造
相続税は「法定相続人の人数に応じた基礎控除額」を差し引いた課税対象額に対して、10%〜55%の累進税率が適用されます。課税額が大きくなるほど、税率も高くなる仕組みです。
例:課税遺産総額が3,000万円以下であれば税率は15%ですが、6億円を超える場合には55%が適用されます。
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されるため、相続人の人数が多いほど課税対象額が小さくなります。
贈与税の税率構造
贈与税も累進課税方式ですが、相続税よりも税率が厳しく設計されています。特に、「特例贈与」か「一般贈与」かで税率が異なる点が重要です。
- 特例贈与:直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の子や孫への贈与
- 一般贈与:それ以外の贈与(兄弟・親戚・配偶者など)
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、それを超えた金額については最大55%の税率が課せられます。
相続税と比べて、少額でも課税されやすい点が特徴です。
税率の違いが与える影響
同じ金額を移転する場合でも、相続と贈与では課税額が大きく異なる可能性があります。たとえば、3,000万円を一括で贈与した場合、贈与税では約690万円〜800万円以上になるケースもありますが、相続税であれば基礎控除の範囲内で非課税になる可能性もあります。
そのため、税率の比較だけでなく、控除や課税方法も含めてトータルで判断することが重要です。
相続税と贈与税の申告と支払い時期
相続税と贈与税は、いずれも財産を取得した人が税務署に申告・納税する義務がありますが、申告期限や支払い方法が異なるため注意が必要です。
相続税の申告・納付時期
相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。申告義務がある人は、財産の取得額に応じて税務署へ申告書を提出し、同じく10か月以内に納付を行う必要があります。
また、原則として金銭で一括納付する必要がありますが、まとまった現金が用意できない場合には、延納や物納(不動産などでの納税)といった制度も活用できます。
贈与税の申告・納付時期
贈与税は「贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで」に申告・納税を行う必要があります。1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合、その超えた金額に対して課税されます。
申告は受贈者本人が行い、納付も同様に申告期限内に完了しなければなりません。延納制度はありますが、相続税に比べると利用のハードルが高く、原則として一括での納付が求められます。
申告しないとどうなる?
期限内に申告や納税を行わない場合、加算税や延滞税が課されるリスクがあります。特に贈与税については「もらったことを知られなければ大丈夫」と誤解されることもありますが、税務署は名義変更や資金移動を通じて把握可能です。
そのため、早めに税理士など専門家に相談し、適切な時期に正しい申告を行うことが大切です。
相続税と贈与税の節税対策
相続税や贈与税は、正しい知識と計画的な対策を取ることで、無理なく節税につなげることが可能です。ここでは代表的な節税策を、相続税と贈与税に分けて紹介します。
相続税の節税対策
① 生前贈与の活用
相続開始前にあらかじめ財産を分割しておくことで、相続時の課税対象財産を減らすことができます。ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象に含まれるため、早めの計画が肝心です。
② 配偶者控除の活用
配偶者が財産を相続する場合、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税になります。これにより、大部分の財産を無税で移転することが可能です。
③ 小規模宅地等の特例
居住用や事業用の宅地については、一定の条件を満たせば土地評価額を最大80%減額できます。土地が相続財産の多くを占めるケースでは、極めて有効な対策です。
④ 不動産の有効活用
預金をアパートなどの収益物件に変えることで、課税評価額を圧縮しながら安定収入を確保することも可能です。ただし、リスク管理と長期的視点が必要です。
贈与税の節税対策
① 暦年贈与の活用
毎年110万円以内の贈与であれば、申告・納税なしで贈与可能です。長期的にコツコツと資産を移転するには最も基本的な方法です。
② 相続時精算課税制度の利用
60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対して、2,500万円まで非課税で贈与できる制度です。ただし、一度選択すると暦年課税には戻れないため、慎重な検討が必要です。
③ 教育資金・結婚資金の一括贈与
一定の条件のもとで、教育資金は最大1,500万円、結婚・子育て資金は最大1,000万円まで非課税で贈与できる制度もあります(2024年以降は制度内容が段階的に変更されていますので、最新情報の確認が必要です)。
節税には必ずルールと上限があるため、安易な贈与や不動産活用だけでなく、法改正や相続人の状況を踏まえた専門的判断が重要です。可能であれば、税理士などの専門家に早めに相談することで、無駄のない対策が立てられます。
相続税と贈与税の違いを踏まえた最適な選択
相続税と贈与税、どちらを活用するのが得なのか?
この問いに対する答えは、「ご家族の状況や資産の内容、将来のライフプラン」によって変わります。一概にどちらが有利とは言えず、複合的な視点で検討する必要があります。
贈与が適しているケース
早めに資産を分けておきたい場合
子どもや孫に資産を計画的に移したいと考えるなら、暦年贈与や相続時精算課税制度の活用が有効です。特に教育資金や住宅取得資金など、目的が明確な支出であれば非課税制度が利用できる可能性もあります。
相続時のトラブルを回避したい場合
生前に財産の分配をある程度決めておくことで、相続人間の争いを予防できるケースもあります。
相続が適しているケース
配偶者や法定相続人が中心となる相続
相続税には配偶者控除や基礎控除、小規模宅地等の特例などがあり、贈与よりも税負担が少なくなることが多いです。
不動産を中心とした資産構成
相続により不動産を引き継ぐ場合、評価額を大きく減額できる特例制度があります。贈与ではこれらの特例が適用されないため、相続による承継の方が有利になることがあります。
将来的な法改正の影響にも注意
税制は定期的に見直しが行われており、贈与税と相続税の一体化などが議論されています。
そのため、現在の制度を前提にした対策が、数年後には効果を失ってしまう可能性も否定できません。常に最新の制度を確認しながら、柔軟に見直す姿勢が重要です。
最適な選択のために
最終的には、家族構成・財産の種類・ライフプラン・相続人同士の関係性などを総合的に考慮しながら、どちらを選択すべきか判断することが求められます。
そのためには、専門家による具体的なシミュレーションやアドバイスを受けることが非常に有効です。
まとめ
相続税と贈与税は、どちらも財産を受け取る際にかかる税金ですが、課税のタイミング・税率・控除制度・申告方法などに明確な違いがあります。
一般的に、贈与は「生前に資産を移す」方法として柔軟に活用できる一方で、税率が高くなりがちです。一方、相続には特例や控除が多く用意されているため、条件次第では税負担を抑えやすいという利点があります。
また、どちらの方法も計画的に行わなければ節税にならないどころか、かえって負担が増えてしまうリスクもあります。「早めの情報収集と専門家への相談」が、損をしないための第一歩です。
大切な財産を円満に次世代へ引き継ぐためにも、ご自身やご家族の状況に応じた最適な対策を検討してみてはいかがでしょうか。
相続や贈与でお悩みの方へ ― 無料相談をご活用ください
「相続税と贈与税の違いは分かったけれど、自分のケースではどうすればいいのか分からない」
そんな方は、専門家による無料相談を活用してみませんか?
税制は複雑で、同じ財産額でもご家族の状況や財産の種類によって最適な対策は異なります。
専門家の視点でシミュレーションを行えば、税負担を軽減し、将来のトラブルも未然に防ぐことが可能です。
当事務所では、相続税・贈与税に関する無料相談を実施しています。
お気軽にご相談いただければ、お一人おひとりに最適な対策をご提案いたします。
今のうちに対策を始めて、将来に備えませんか?
ご相談はオンライン・対面いずれも可能です。詳しくは下記のリンクからご覧ください。